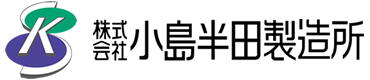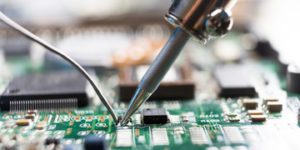はんだ不濡れの原因と対策
コテ付けではんだの不濡れを起こす一番の原因は熱不足によるものです。 熱不足になる要因として次のようなものが挙げられます。 ・コテ先温度が低い。 ・コテ先形状が不適切。ハンダ付け部にコテ先がしっかりと接していない。 ・コテ先の熱容量が足りない。大きい部品や、熱が逃げやすいはんだ付け部では、熱容量の小さい細いはんだコテではなかなか温度は上がりません。 ・コテを当てている時間(加熱時間)が足りない。はんだ付け部にはんだを供給してはんだが溶けても、はんだが濡れ広がるまで時間がかかる場合があります。しっかりとはんだが濡れたのを確認してコテを離してください。 基板や部品が吸湿していると、その水分が突沸する事ではんだを弾き飛ばしてしまい(※飛散)、不濡れの原因になります。 また、そもそも水分を含んでいるということは、部品や基板の酸化が進んでいることが考えられるため、もともと濡れにくい状態にあります。金属表面が強固な酸化物で覆われている場合、フラックスで酸化物を十分に除去する事が出来ず、はじきや不濡れが発生します。 また、基板や部品の汚れも不濡れの原因になります。 ※はんだやフラックスの飛散に関しては、次のページでも説明しています。 はんだ、フラックスの飛散原因と対策について 通常、基板の銅部分には、酸化を防止するためにメッキをかけたりプリフラックスを塗布したりして大気中に曝露しないようにされています。 基板自体の保管状態が悪いと、その表面のプリフラックスやメッキが劣化します。 またメッキが薄くなっている場合は、金属化合物が表面に露出して、それ自体はんだが濡れ難いです。 一般的に銅は濡れやすい金属ですが、ニッケル、ステンレス、アルミは濡れにくい金属です。 それらにはんだ付けする場合には、通常のはんだでは濡れにくいこともありますので、はんだ付けする金属に合わせて適切なフラックスを使用する必要があります。 弊社では、ステンレス用糸はんだとして「UX」を、糸はんだでニッケルにはんだ付けする際の補助フラックスとして「ニッケル用液体フラックス」をご用意しております。 製品一覧 ニッケル用液体フラックス 不濡れの原因としては、次の事が考えられます。 (1)コテ先及びはんだ付け部分の温度が十分に上がっていない (2)はんだ付けする基板や部品が吸湿や汚れがある (3)基板ランドのプリフラックスやメッキが劣化している (4)はんだ付けする金属に合わせて適切なフラックスを使用していない 対策としては、 (1)使用するはんだごての特徴を確認し、コテ先、はんだ付け部に熱を伝え、適正な温度加熱してはんだ付けする 参考:はんだ付けの基礎知識や注意点 (2)基板や部品の保管管理をして、また吸湿や汚れがないかどうか確認する (3)基板ランドのメッキが剥げていないかどうかを確認する (4)はんだ付けする金属に適切なフラックス(やに入りはんだ)を使用しているかどうかを確認する